ある日、息子が「散歩に行ってくる」と言いました。
ほんの10分程度の外出。
私には、その言葉が「新しい扉の音」に聞こえました。
空気の匂いも、人の気配も、彼にとっては久しぶりの感覚。
帰ってきた息子は、何も言わずに水を飲んで部屋に戻りました。
その背中の向こうに
世界とのつながりが少しだけ戻ってきた気がしたのです。
外に出るのは「目的」ではなく「感覚」
不登校の子が外に出るのは、
何かをするためではなく、外の空気を思い出すため。
それを親が成果として捉えてしまうと
またプレッシャーに変わってしまいます。
だから私は、「出られた」ではなく
「外の風に触れられた」と考えるようにしました。
行動を評価するより、感覚を尊重するほうがずっと大切なのです。
「外」に慣れる前に「人」に慣れる
息子が最初に関わった“外の人”は、
コンビニの店員さんでした。
「いらっしゃいませ」
「ありがとうございました」
たったそれだけの会話でも、彼にとっては大きな再会。
私はその日、何も聞きませんでした。
でも、夕飯のときに少し笑っていた彼を見て
「あ、外はもう怖くないのかもしれない」と思いました。
親ができることは「世界を先に信じる」こと
社会のニュースを見ていると、
つい「危ない」「怖い」と思ってしまいます。
けれど、親が世界を信じられないままでいると、
子どもも外に希望を感じられません。
だから私は、
「外にもいい人がいる」「優しさもちゃんとある」
そうやって小さく言葉にする練習を始めました。
親が信じることが、子どもにとっての“道標”になります。
いま思うこと
外の世界は、たしかに広くて、時に冷たい。
でも、そこにまた踏み出せたなら──
それは、立派な「再生」の証です。
歩幅は小さくていい。
日常の中に、少しずつ“外の音”を混ぜながら、
また世界とつながっていけたらいい。
親ができるのは、その背中に静かに風を送ること。
「いってらっしゃい」と笑って送り出せることが
とても大切なのだと思っています。

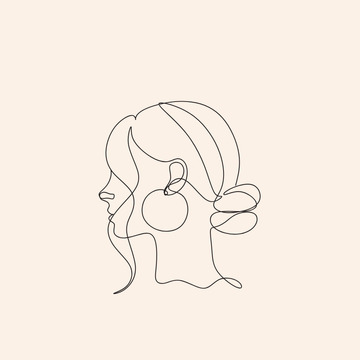




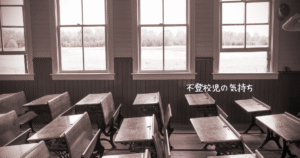
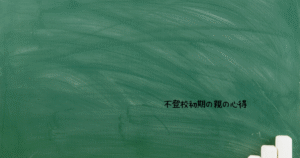

コメント