我が子が不登校の時
私はずっと
「どうすれば動けるようになるのか」
ということばかり考えていました。
朝起きられた日は少し安心して
また寝てしまうと焦って落ち込む。
“行動がある=前進”
“行動がない=停滞”
そんなふうに
無意識に自分を追い詰めていました。
そして私が焦れば焦るほど
大切なわが子まで追い詰めていたのかもしれません。
動かそうとすると、さらに止まる
ある時、息子に
「たまには外に買い物に行かない?」と声をかけたら
その瞬間、顔が強張って
何も言わずに部屋へ戻ってしまいました。
それを見て気づきました。
「動いてほしい」と願う言葉は
『今のあなたでは足りない』というメッセージにもなることを。
子どもにとって
動けない時間もちゃんと回復している時間だったのです。
信じることは、黙ること
私はその日から
「次はどうするの?」と聞かない練習を始めました。
質問をやめて、代わりに紅茶を入れる。
返事を待たずに「おはよう」だけ言う。
その沈黙の中で、
少しずつ我が家の空気がやわらかくなっていきました。
言葉を減らすと
子どもが“安心できる沈黙”の中で
少しずつ自分を取り戻していることに気が付きました。
回復には“静かな伴走”が必要
不登校の子どもは、
「誰かに引っ張られたい」よりも
「誰かがそばにいてほしい」と思っています。
だから、親ができるのは“先導”ではなく“伴走”。
親が不安なのに、子ども自身が不安でないわけがないのです。
何も言わずに同じ時間を共有する。
それが、いちばんのサポートになるのだと学びました。
いま思うこと
行動を促すより、
“信じて待つ”ほうがずっと難しい。
子どもは親の焦りを敏感に感じ取ります。
だからこそ、親が落ち着いていられることが最大の支援になる。
焦らない勇気。
信じる沈黙。
それが「再生の時間」を育ててくれるのです。
この『グッと我慢』の時間こそ
親が一番成長する時間だったと今は感じています。

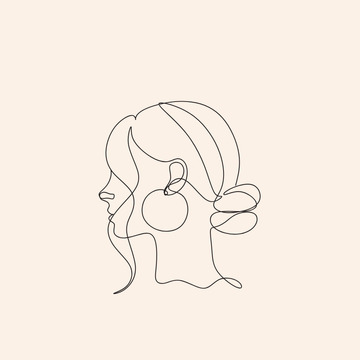



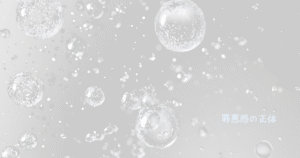

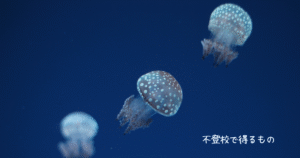


コメント